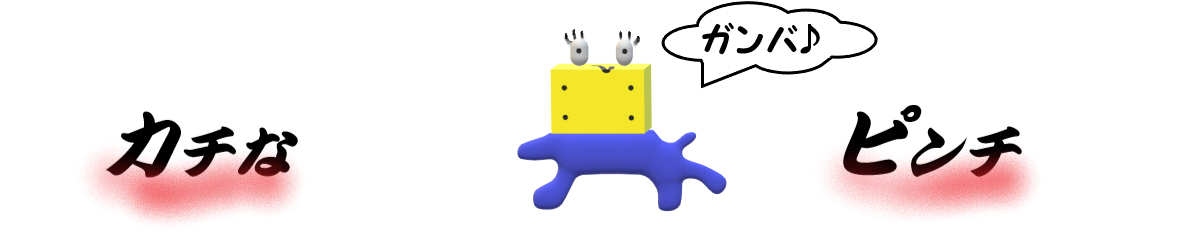クライミングのムーブの1つにランジがあります。よくメディアでボルダリングが紹介されるときは必ずと言っていい程このランジが出てきます。
遠いホールドに飛びついて、足は宙ぶらりん。腕の力だけで浮いている状態。
ボルダリングではこういったダイナミックムーブが映えますし実際決まると周りも盛り上がります。
ランジやダブルダイノは派手でかっこいいですが苦手な人も多いのではないでしょうか?
何が嫌ってランジ・ダブルダイノ共に失敗したときの着地が1番怖いですよね。吹っ飛ばされたり、回転しながら落ちたり。
僕はランジ自体そこまで嫌いではなかったのですが(上手下手別として)、最近ランジもしくはダブルダイノをしなければいけない課題に出会い毎回ボコボコにされています。
距離がだせないから始まり、距離がだせても全く止まらない⇒一瞬止まるが振られて落ちる⇒ダブルダイノならどうだ⇒数秒止まるがやっぱり振られ落ち⇒絶望
という流れで今は絶望で思考停止しています。
最後を⇒【止まった】にする為にも
今一度ランジ&ダブルダイノについて1から考え直したいと思います。
ランジ・ダブルダイノ・サイファーの違い
ランジ
狙いのホールドに片手で飛びつく。
片手が残る場合もあれば外れてしまう場合もある。
外れてしまった場合は壁を抑えて振られを抑えましょう。
ダブルダイノ
狙いのホールドに両手で飛びつくムーブ。
次に狙っているホールドが悪くて手が残らない場合に両手でがっちりと保持する事が出来るが、振られる量も大きくなる。
完全に空中に浮く瞬間があるのがこのムーブの特徴です。
サイファー
上級者向けであまり多用するムーブではないがサイファー必須の課題もあるので覚えておきたいムーブである。
両手片足がついた状態で、手が届かないホールド(足がきれてしまう)へ飛びつくムーブ。
ホールドに乗っていない方の足を振り子のように右左にスイングさせ、その勢いを使って距離を出す。遠心力を利用しつつ飛びつくムーブなのです。
手が届かないホールドに飛びつくということでランジと似ています。
しかしランジは上に飛ぶ時、サイファーは横や斜め上に飛ぶときなどなんとなく使い分けがあります。(もちろん例外もあります)
具体的にはサイファーは足場が1つしかない時に活用します。
個人的にはクライミングのムーブの中で名前・動き共に1番カッコイイのがサイファーです。
ランジ・ダブルダイノのコツ
ランジ・ダブルダイノで重要なのは
- しっかりとしたタメを作ること
- 壁にそって飛ぶこと
①しっかりとしたタメを作る
距離を出すには足の蹴り、手の引きどちらも必要となります。
蹴る力は屈伸により膝を深く曲げることで作られ、引きつけは腕を伸ばし気味にした方がより力が入ります。
ボルダリングの基本姿勢である壁にはいることをせず、腰を大きく壁から離すことによりタメを作ります。
距離を出すのは足。方向を決めるのは手です。
足を蹴り上げる・腕を引き付けるこの2つのバランスをうまくとることによって目標のホールドまでの距離が出るようになるのです。
ランジ・ダブルダイノをする時に腰をブンブンと何回も振る人がいますが、そこまで振る必要はありません。基本的にタメを作れたらそのまま飛び出しましょう。
②壁にそって飛ぶ
初めのうちはとても怖いと思うのですが、かなり重要です。
壁から離れて飛ぶと掴みたいホールドからも離れてしまい上手く保持する事が出来ません。まったく取れないのならまだいいのですが、中途半端に掴んでしまい振られで落ちると自分の体を制御できず最悪頭からマットに落ちることになります。
イメージとしては腕で壁を思いっきり引き寄せ、足の伸びは壁の形状に沿わすといった感じですね。
頭・腰は壁にぶつけるぐらいの気持ちで行くと上手くいきます。
実際ぶつかることなんて滅多にないですから。
腕の引き付けが終わった瞬間、ホールドを蹴りだしジャンプできればタイミングとしては最高です。
上級者テクニック
ランジの成功率を上げるテクニックを紹介します。
ダイアゴナルのコツとして、進行方向の逆を見るは有名ですがそれをランジでやります。
取りに行くホールドを見るのではなく残るほうの手を見るのです。
実は視線で体の向きが決まってきます。例えば右に視線を送ると右肩が開きますよね?逆に左肩は中に入ります。
残るほうの手を見ることによって取りに行く手が少し伸び距離が出せるのです。
そして残るほうの手は肩が開くことにより引いている状態から押すに切り替えることができます。押すことにより振られと逆方向にも力のベクトルが向き、振られを相殺させ結果止まるようになります。
飛びながら引く押すを考えるのは至難の業。見る向きを逆にするだけで勝手にこの動きをする事ができるというわけです。
ランジ・ダブルダイノまとめ
基本から上級者向けのテクニックまでを紹介しましたが、理論とかテクニックというのは結局のところ保持力のない弱者のためにあるという言葉を思い出しました。
はい。僕には理論やテクニックが必要です。
それで登れなかった課題が登れるようになるのならいくらでも調べて勉強します。
本当は何もかも押し通せる保持力お化けになりたいですが、まだまだ努力が足りていません。
足りてなくても登りたいなら頭を使うしかないのです。逆に頭を使えば登れる可能性があるのがボルダリングの魅力でもあります。
頭を使うのはあまり得意ではないですが、登れなかった課題が登れるようになった瞬間が何よりも気持ちいいので頑張ります。では